突然の訃報は、誰にとっても動揺し、悲しいものです。「何から手をつければいいのだろう」「マナーが分からなくて不安だ」「失礼のないようにしたい」…そんな戸惑いや不安を感じる方は少なくありません。
 新米くん
新米くんいざという時、葬儀に関する知識がないと、「故人やご遺族に対して失礼にあたらないか」「周囲からどう見られるだろうか」といった大きな不安を感じてしまうものです。特に、服装のマナー、香典の金額や書き方、当日の流れ、焼香の作法などは、事前に知っておかないと当日になって慌ててしまったり、意図せずマナー違反をしてしまったりする ケースが少なくありません。



そこでこの記事では、長年冠婚葬祭に関する情報に携わってきた経験から、葬儀に参列する際、あるいは執り行う際に 最低限知っておくべき服装のマナー、香典の相場と準備、当日の流れ、供花の手配、そして一般的な費用相場まで、 葬儀に関するあらゆる疑問を解消できるよう網羅的に解説します。



この記事を最後まで読めば、葬儀に関する基本的な知識が身につき、「何を用意し、どう振る舞えば良いのか」が明確になります。 これにより、いざという時に慌てず、失礼なく、心から故人を見送るための準備が整います。最後には「持ち物チェックリスト」もご用意しました。



突然の悲しみに際しても、少しでも落ち着いて故人との最後のお別れに臨めるよう、この記事があなたの一助となれば幸いです。ぜひ最後までお読みください。
1. 【葬儀の基本的な流れ】臨終から葬儀後まで


まず、ご逝去から葬儀が終わるまでの一般的な流れを把握しましょう。全体の流れを知っておくことで、いつ何が必要になるのか見通しが立ち、落ち着いて対応しやすくなります。



葬儀は、臨終 → 安置 → 打ち合わせ → 納棺 → 通夜 → 葬儀・告別式 → 火葬 → 骨上げ → (繰り上げ)初七日法要 という流れで進むのが一般的です。
この一連の流れは、故人様を偲び、弔い、社会的なお別れをするための大切な儀式として定着しています。



各ステップにはそれぞれ意味があり、手順を踏むことで、ご遺族も参列者も心の整理をつけながら故人様をお見送りすることができます。



以下に、各ステップの内容をもう少し詳しく見ていきましょう。(地域や宗派、葬儀の形式によって多少異なる場合があります)
葬儀の流れ 安心ガイド
ご臨終・逝去確認
- 医師による死亡確認後、死亡診断書を受け取ります。
搬送・安置
- 故人様をご自宅や安置施設へ。枕飾りを整えます。
葬儀社との打ち合わせ
- 日程、場所、形式、費用等を決定。関係各所に連絡。
納棺の儀
- 近親者で故人様の身支度を整え、棺に納めます。
お通夜
- 葬儀前夜、故人と過ごす最後の夜。一般弔問も。
葬儀・告別式
- 故人の冥福を祈り、社会的なお別れをする儀式です。
火葬・骨上げ
- 火葬場で火葬し、遺骨を骨壷に納めます(拾骨)。
繰り上げ初七日法要・精進落とし
- 火葬後、法要と食事の席を設けることが増えています。
以上が、臨終から葬儀後までの大まかな流れです。この流れを頭に入れておくことで、準備や参列がスムーズになります。



不明な点は、遠慮なく葬儀社に確認しましょう。



2. 【葬儀の服装マナー】男女別・持ち物・注意点


葬儀に参列する際の服装は、故人や遺族への弔意を表すための重要なマナーです。場にふさわしくない服装は、失礼にあたるだけでなく、ご自身が気まずい思いをしてしまう可能性もあります。



葬儀・告別式に一般参列者として参列する場合、男女ともに「準喪服(じゅんもふく)」と呼ばれる服装が基本です。お通夜の場合は「略喪服(りゃくもふく)」でも良いとされていますが、近年ではお通夜から準喪服を着用する方も増えています。
喪服を着用することは、「故人を悼み、悲しみを共有しています」という意思表示になります。華美な装飾を避け、肌の露出を控えた控えめな服装をすることで、厳粛な儀式の場にふさわしい敬意を示すことができます。
喪服の種類について
簡単に喪服の種類に触れておきます。
喪服の種類とマナー
正喪服 (せいもふく)
- 最も格式の高い喪服です。
- 喪主や三親等までの遺族が着用します。
- 例: 和装(紋付)、モーニングコート、黒無地五つ紋付、ブラックフォーマル。
準喪服 (じゅんもふく)
- 一般的な喪服です。
- 一般参列者や遺族も着用します。
- 例: ブラックスーツ、ブラックフォーマル(ワンピース、アンサンブル等)。
略喪服 (りゃくもふく)
- 急な弔問やお通夜、「平服」指定時に着用します。
- 普段着ではなく、地味な色合いのものを選びます。
- 例: 黒・濃紺等のダークスーツ、地味なワンピース。






男性の服装(準喪服)
一般参列者の男性は、以下の服装を基本とします。
男性 準喪服 (ブラックスーツ) 着こなしマナー
スーツ
- 光沢のない黒無地(ブラックスーツ)。
- ビジネス用とは違う深い黒を選びます。
- パンツの裾はシングルが正式です。
ワイシャツ
- 白無地のレギュラーカラーが基本です。
- 色柄物やボタンダウンは避けましょう。
ネクタイ
- 光沢のない黒無地のものを選びます。
- 結び目にくぼみを作らず結びます。
- ネクタイピンは使用しません。
靴
- 黒の革靴。光沢や金具がないもの。
- ストレートチップかプレーントゥが最適。
- 紐で結ぶタイプがよりフォーマルです。
靴下
- 黒無地のものを着用します。
- 柄物、ワンポイント、短い丈はNGです。
ベルト
- 黒無地でシンプルなデザインを選びます。
- バックルが派手なものは避けましょう。
その他小物
- 時計はシンプルか外すのが無難です。
- カフスは基本付けません(付けるなら黒)。
女性の服装(準喪服)
一般参列者の女性は、以下の服装を基本とします。
女性 準喪服 (ブラックフォーマル) 着こなしマナー
服装
- 光沢のない黒無地のワンピース、アンサンブル、スーツを着用します。
デザイン
- 露出は控えめに。襟元は詰まり気味。
- 袖は五分~長袖、丈は膝下~が基本。
- 体のラインが出すぎないものを選びます。
ストッキング
- 黒の薄手(30デニール以下が目安)。
- 厚手タイツ、網、柄、肌色はNGです。
靴
- 黒の布製か革製パンプス。光沢NG。
- 飾りのないシンプルデザイン。
- ヒールは3~5cm程度。太すぎず。
- オープントゥ、サンダル、ブーツはNG。
バッグ
- 黒の布製フォーマルバッグが基本。
- 光沢や目立つ金具、殺生連想の革は避ける。
- 袱紗などが入る小ぶりなサイズが良いです。
アクセサリー
- 基本は結婚指輪以外は外します。
- 付けるなら一連パールネックレス(白/黒/灰)。
- 二連以上や揺れるデザインはNGです。
- イヤリング等も一粒パール/黒曜石など。
髪型
- 清潔感を意識し、まとめ髪が基本。
- 低い位置で束ねる、シニヨンなど。
- 派手な髪飾りは避け、黒のゴム等で。
メイク・その他
- ナチュラルメイク(片化粧)を心がけます。
- 口紅やチークは控えめに。ノーメイクも注意。
- ネイルは落とすか目立たない色。香水NG。
子供・学生の服装
学校の制服があれば、それが正式な喪服となります。靴下や靴も制服規定に合わせますが、なければ黒や白の無地のものを選びましょう。
制服がない場合は、黒、濃紺、グレーといった地味な色の服装を選びます。男の子なら白いシャツに黒や紺のズボン、ブレザーがあれば羽織ります。女の子なら白いブラウスに黒や紺のスカートやワンピースが良いでしょう。キャラクターものや派手なデザインは避けます。



持ち物リスト
以下のものを準備しておくと安心です。
葬儀・お通夜の持ち物リスト
香典 (袱紗に包んで)
- 不祝儀袋に入れ、袱紗に包んで持参。
- 受付で袱紗から取り出して渡します。
袱紗 (ふくさ)
- 香典を包む布。弔事は寒色系(黒/灰/紫等)。
- 紫色は慶弔どちらにも使えて便利です。
数珠 (じゅず)
- 自身の宗派のものがあれば持参します。
- なければ無理に用意する必要はありません。
- 貸し借りはマナー違反とされます。
ハンカチ
- 白無地または黒無地のものを用意。
- レース縁取り程度なら可。タオル地はNG。
予備ストッキング (女性)
- 黒の薄手のものを用意しておくと安心。
- 伝線してしまった場合に備えます。
その他
- 必要に応じて、黒など地味な色の傘。
- 冬場は黒や紺などの地味なコート。
服装に関する注意点・NG例
葬儀・お通夜 服装・持ち物 NG マナー
NG: 殺生を連想させるもの
- 動物の革(ヘビ・ワニ等)や毛皮は避ける。
- 靴やバッグは光沢ないシンプルな革なら可。
NG: 光沢のある素材
- サテンやエナメルなど光る素材は避ける。
- 弔事の場にはふさわしくありません。
NG: 過度な肌の露出
- 肩、胸元、背中の開き、ミニ丈、ノースリーブNG。
- 夏場でも肌の露出は最低限に。
NG: 華美なアクセサリー
- 結婚指輪以外は基本的に外します。
- ゴールド、揺れる物、複数の指輪等はNG。
注意:「平服」の指定
- 「普段着で良い」という意味ではありません。
- 「略喪服で」という意味合いです。
- 迷ったら準喪服が無難です。



葬儀の服装で最も大切なのは、故人を悼み、ご遺族に寄り添う気持ちを表すこと です。清潔感を保ち、控えめで落ち着いた装いを心がけましょう。



マナーを守ることで、心置きなく故人とのお別れに臨むことができます。
3. 【香典について】相場・袋の選び方・書き方・渡し方マナー


香典(こうでん)は、通夜や葬儀・告別式の際に、故人の霊前に供える金品のことです。






香典は、故人への弔意と、相互扶助の精神に基づき、葬儀費用の負担を少しでも軽減するという意味合いを持っています。



金額の相場やマナーを守り、心を込めて準備し、失礼のないように渡すことが大切です。



香典の習慣は、古くからの「相互扶助」の考え方に由来します。昔は食料などを持ち寄って遺族を助けていましたが、現在では金銭を包む形が一般的になりました。






適切な金額やマナーで香典を渡すことは、故人への敬意と遺族への配慮を示すことにつながります。
香典の金額相場
香典に包む金額は、故人との関係性やご自身の年齢、地域の慣習によって異なります。あくまで目安ですが、一般的な相場は以下の通りです。
| 故人との関係 | 20代 | 30代~40代 | 50代以上 |
|---|---|---|---|
| 親 | 3万円~10万円 | 5万円~10万円 | 10万円~ |
| 兄弟姉妹 | 3万円~5万円 | 5万円 | 5万円~10万円 |
| 祖父母 | 1万円 | 1万円~3万円 | 3万円~5万円 |
| 叔父・叔母 | 5千円~1万円 | 1万円~2万円 | 1万円~3万円 |
| その他の親戚 | 3千円~1万円 | 5千円~1万円 | 1万円~ |
| 友人・知人 | 3千円~1万円 | 5千円~1万円 | 5千円~1万円 |
| 隣近所の方 | 3千円~5千円 | 3千円~1万円 | 5千円~1万円 |
| 勤務先の上司 | 5千円~1万円 | 5千円~1万円 | 1万円~ |
| 勤務先の同僚・部下 | 3千円~1万円 | 5千円~1万円 | 5千円~1万円 |
| (同僚・部下の)家族 | 3千円~5千円 | 3千円~1万円 | 5千円~1万円 |
【金額設定のポイント】
香典の金額を決める際には、いくつか注意したいポイントがあります。
まず、「4(死)」や「9(苦)」 を連想させる数字の金額は避けるのが一般的です(例:4千円、9千円)。






ただし、これまでお伝えした金額相場はあくまで目安です。故人と特に親しかった場合などは、相場より多めに包むこともあります。






金額に迷った場合は、周りの人や親族に相談するのも良いでしょう。特に親族間で金額を揃えるケースもあります。






また、地域の慣習によって相場が異なる場合もあります。






香典袋(不祝儀袋)の選び方
香典袋は、宗教・宗派と包む金額によって適切なものを選びます。
失敗しない!香典袋の選び方マナー
Step 1: 宗教・宗派を確認
- 可能なら事前に確認しましょう。
- 不明な場合は、宗教不問の表書きか無地袋を選びます。
Step 2: 水引の色を選ぶ
- 一般的には「黒白」または「双銀」。
- 関西など地域により「黄白」も使われます。
Step 3: 水引の結び方を確認
- 「結び切り」か「あわじ結び」を選びます。
- (意味:一度きりで繰り返さない)
- 蝶結びは慶事用なのでNGです。
Step 4: 金額に見合う袋を選ぶ
- ~5千円:水引が印刷されたもの。
- 1~3万円:黒白の実物の水引のもの。
- 3万円~:双銀水引や高級和紙など格上のもの。
香典袋の書き方
表書きに用意するもの
- 薄墨の筆または筆ペン 「悲しみの涙で墨が薄まった」「急いで駆けつけた」という意味が込められます。
- 通常の黒の筆ペンやサインペン 薄墨がない場合は許容されます。
- ボールペンや万年筆 事務的な印象を与えるため避けましょう。
【書き方の手順】
香典袋の表書きの書き方 (水引の上)
仏式 (浄土真宗以外)
- 「御霊前」と書くのが一般的です。
- 四十九日を過ぎると「御仏前」とします。
仏式 (浄土真宗)
- 時期を問わず「御佛前」または「御仏前」と書きます。
- (故人はすぐに仏になる、という教えから)
神式
- 「御玉串料」「御榊料」と書きます。
- 「御神前」も使われます。
キリスト教式
- 「御花料」「献花料」が一般的です。
- カトリックでは「御ミサ料」も使われます。
- 蓮の花がデザインされた袋は仏式用なのでNG。
宗教が不明な場合
- 「御霊前」と書けば、多くの場合で使えます。
- ただし浄土真宗には注意が必要です。
- 宗教不問タイプの香典袋を選ぶのも良いでしょう。
香典袋の名前の書き方 (水引の下)
個人の場合
- 表書きより少し小さめに、氏名をフルネームで書きます。
夫婦の場合
- 中央に夫の氏名を書きます。
- その左隣に、妻の名前のみを書きます。
連名 (3名まで)
- 目上の方(または代表者)を中央に書きます。
- 序列に従い、左へ順に他の人の氏名を書きます。
連名 (4名以上)
- 代表者の氏名を中央に書きます。
- その左に「外一同」または「他 〇名」と書き添えます。
- 全員の氏名・住所・金額を書いた別紙を中袋に入れます。
会社として出す場合
- 中央に代表者の氏名を書きます(役職も入れてOK)。
- 氏名の右肩に、会社名をやや小さめに書きます。
部署・グループの場合
- 「〇〇株式会社 〇〇部一同」のように書きます。
- この場合も別紙に全員の氏名と各自の金額を記載します。
中袋 (中包み) の書き方
表面:金額の書き方
- 中央に包んだ金額を旧漢字(大字)で縦書きします。
- 「金」を頭に、「也」は末尾に付けても付けなくても可。
- 例: 伍仟圓 (五千円), 壱萬圓 (一万円),
参萬圓 (三万円), 伍萬圓 (五万円) 等
裏面:住所・氏名の書き方
- 裏面の左下に、郵便番号、住所、氏名をフルネームで書きます。
- 縦書きで記入するのが基本です。
- 遺族が香典返しを手配する際に必要な大切な情報です。
中袋がない場合
- 香典袋の裏面の左下に、住所・氏名・金額を直接書きます。
- この場合の金額は、算用数字(アラビア数字)で書いても構いません。
お金の入れ方
香典に入れるお金の入れ方マナー
新札は避ける
- 「不幸を予期して準備していた」と受け取られないように、新札は避けます。
- もし新札しかない場合は、一度軽く二つに折ってから入れましょう。
- 汚れたお札や破れたお札は失礼にあたるので避けましょう。
お札の向き
- 中袋の表面(金額を書く面)に対して、お札の肖像画(顔)が 裏側 かつ 下側 になるように入れます。
- (意味:「悲しみに顔を伏せる」)
- 複数枚入れる場合は、全てのお札の向きを揃えましょう。
香典の渡し方
香典を準備したら、次は渡し方です。失礼のないよう、マナーを守って渡しましょう。
袱紗(ふくさ)に包む
香典袋は必ず袱紗(ふくさ)に包んで持参します。裸で持ち歩くのはマナー違反です。






弔事用の袱紗(紫、紺、緑、グレーなど寒色系のもの)を用意し、左開き になるように包みます。(※慶事は右開きです)
渡すタイミング
- 受付がある場合: 通夜・葬儀会場に到着したら、まず受付で記帳(または名刺を渡す)し、その際に香典を渡します。
- 受付がない場合: 遺族に直接手渡すか、指示があれば祭壇に供えます。直接渡す場合は、タイミングを見計らい、遺族が少し落ち着いた時に。
渡し方
- 受付の方(またはご遺族)の前で、袱紗を開きます。
- 香典袋を取り出し、袱紗をたたみます(または下に敷きます)。
- 相手から見て表書きの名前が読めるように向きを変え、両手を添えて差し出します。
添える言葉
渡す際には、短いお悔やみの言葉を添えます。






- 「この度は誠にご愁傷様でございます。心よりお悔やみ申し上げます。」
- 「この度は突然のことで、お慰めの言葉もございません。どうぞ御霊前にお供えください。」
などの言葉を選び、声のトーンも抑えめに話しましょう。
香典を辞退された場合
近年、遺族の意向で香典を辞退されるケース(香典辞退)が増えています。その場合は、遺族の気持ちを尊重し、無理に渡そうとしない のがマナーです。






受付で香典辞退の旨を伝えられたら、「さようでございますか。それでは失礼いたします。」などと述べ、香典は持ち帰ります。記帳は勧められたら行い、弔意を示しましょう。
どうしても何か弔意を示したい場合は、後日改めて供花や供物を送る(これらも辞退されていないか確認が必要)、弔電を送る、といった方法を検討します。
4. 【葬儀・告別式のマナー】受付・焼香・お悔やみの言葉など


葬儀・告別式は、故人を偲び、遺族と共に冥福を祈る厳粛な儀式です。参列する際は、故人への敬意と遺族への配慮を忘れず、マナーを守って行動することが求められます。
会場への到着時間から受付、焼香、お悔やみの言葉に至るまで、一連の作法やマナーを理解し、厳粛な態度で臨むことが大切です。 適切なマナーで参列することは、故人への弔意を正しく伝え、遺族の悲しみに寄り添う姿勢を示すことにつながります。また、儀式の円滑な進行にも協力することになり、参列者自身も落ち着いて故人とのお別れに集中できます。
会場到着と受付
到着時間: 一般的に、葬儀・告別式の開始時刻の10分~15分前 には会場に到着するようにしましょう。






早すぎる到着は、準備中の遺族や関係者の負担になることがあります。逆に、遅刻は厳禁ですが、やむを得ず遅れた場合は後述します。
会場に入る前に: 会場に入る前に、コートやマフラー、帽子などは脱いでおくのがマナーです。携帯電話はマナーモードに設定するか、電源を切っておきましょう。
葬儀の受付 スムーズな流れとマナー
お悔やみの言葉を述べる
- 受付係に「この度はご愁傷様です」など、簡潔にお悔やみを伝えます。
記帳する
- 芳名帳(カード)に氏名・住所を丁寧に記入。
- 代理の場合は代理である旨と本人氏名も。
香典を渡す
- 袱紗から出し、相手向きで両手で渡します。
- 「御霊前にお供えください」等添えて。
返礼品を受け取る
- 会葬御礼品などを受け取る場合があります。
- 一礼して、丁寧に受け取りましょう。
会場内へ進む
- 受付係の案内に従います。
- 私語は慎み、静かに会場内へ進みましょう。
遅刻は厳禁! 万が一遅れた場合は、式の妨げにならないよう静かに入室し、係員の指示に従ってください。受付は閉式後に済ませましょう。






会場内でのマナー
私語は慎む
会場内では静粛に。知り合いを見かけても、大きな声での挨拶や長々とした世間話は控え、軽く目礼する程度に留めましょう。






携帯電話
再度確認し、マナーモードまたは電源オフに。式中に着信音が鳴らないように細心の注意を払います。
着席
案内があればその指示に従います。特に指定がなければ、一般参列者は前から詰めて座るのが基本ですが、遺族・親族席(通常は前方)を避けて着席します。
友人・知人同士で固まらず、一人で参列した場合でも空いている席に座りましょう。
会場内では静粛を保ち、携帯電話の電源はオフにしましょう。着席は案内に従い、私語は慎むのが基本です。
焼香の作法
焼香は、故人の冥福を祈り、自身の心身を清めるための大切な作法です。宗派によって回数などが異なりますが、ここでは一般的な立礼焼香(立ったまま行う焼香)の手順を説明します。
【立礼】焼香の基本的な手順とマナー
進み出て一礼
- 順番が来たら席を立ち、まずご遺族に一礼します。
- その後、焼香台の手前まで進みます。
祭壇に一礼
- 焼香台の前に立ち、祭壇の遺影等に向かって深く一礼します。
抹香をつまむ
- 右手の親指・人差し指・中指の三本で抹香を少量つまみます。
押しいただく (宗派による)
- つまんだ抹香を額の高さに捧げます。
- 浄土真宗等では行いません。迷ったら省略可。
香炉にくべる
- 抹香を香炉(火のある方)の中に静かに落とします。
繰り返す (1~3回)
- 手順3~5を1~3回繰り返します(宗派による)。
- 案内に従い1回でも問題ありません。
合掌・礼拝
- 焼香後、祭壇に向かって深く合掌し、故人の冥福を祈ります。
再度、祭壇に一礼
- 合掌の後、改めて祭壇に向かって深く一礼します。
退いて一礼
- 祭壇前から数歩下がり、ご遺族に再度一礼してから自席に戻ります。






数珠(念珠)の扱い方
数珠は仏教徒にとって大切な法具です。
- 持ち方: 焼香の順番を待つ間や着席中は、基本的に 左手 で持ちます。房(ふさ)は下に垂らすようにします。
- 合掌時: 合掌する際は、宗派によって異なりますが、両方の手の親指と人差し指の間に掛ける、二重にして左手にかける、などの方法があります。
- 注意点:
- 数珠は個人のものですので、貸し借りはしません。






- 畳の上や椅子の上に直接置くのは避けましょう。バッグにしまうか、常に手に持つ、またはハンカチなどの上に置きます。
- 仏教徒でない場合や、持っていない場合は、無理に用意する必要はありません。
数珠の貸し借りはNG! 数珠は個人の大切な法具です。忘れた場合は持たずに参列しても問題ありません。
お悔やみの言葉
遺族にお声がけする際は、悲しみに配慮し、手短に心を込めて伝えることが大切です。
基本的な言葉:
- 「この度は誠にご愁傷様(しゅうしょうさま)でございます。」
- 「心よりお悔やみ申し上げます。」
- 「突然のことで、お慰めの言葉もございません。」
- 「安らかなお眠りをお祈りいたします。」
避けるべき言葉・話題(忌み言葉など)
- 重ね言葉: 「たびたび」「ますます」「くれぐれも」など(不幸が重なることを連想させるため)。
- 直接的な表現: 「死ぬ」「死亡」「生きる」「生きていた頃」など(「ご逝去」「お元気な頃」などに言い換える)。
- 不吉な言葉: 「消える」「浮かばれない」「大変なことに」など。
- 宗教・宗派に合わない言葉: 仏式の葬儀で「天国」と言うなど。キリスト教式や神式では「冥福」「供養」「成仏」といった仏教用語は使いません。
- 死因を詳しく尋ねる: 遺族にとって非常につらい質問です。
- 安易な励まし: 「頑張って」「元気を出して」といった言葉は、かえって遺族の負担になることがあります。
- 長話: 遺族は多くの弔問客に対応しています。お悔やみは手短に済ませましょう。






式中の退席について
- やむを得ない事情がない限り、葬儀・告別式の途中で退席するのはマナー違反とされています。
- どうしても中座しなければならない場合は、焼香が終わった後など、式の進行を妨げないタイミングを選び、他の参列者の邪魔にならないように静かに席を立ちます。可能であれば、近くの係員や遺族(親族)に一声かけてから退席するのが丁寧です。
途中退席は原則NG。 やむを得ない場合は、焼香後など式の妨げにならないタイミングで、静かに目立たないように退席しましょう。
葬儀・告別式でのマナーは、故人を敬い、悲しみの中にいる遺族を気遣う心の表れです。
一つ一つの作法を丁寧に、心を込めて行うことが何よりも大切です。もし作法に自信がない場合は、周りの人の動きを参考にしたり、葬儀社のスタッフにそっと尋ねたりしても失礼にはあたりません。



5. 【供花・弔電について】手配方法・相場・マナー


葬儀や告別式に参列できない場合や、香典とは別に故人への深い弔意を示したい場合に、供花(きょうか・くげ)や弔電(ちょうでん)を送ることがあります。これらは、故人を偲び、遺されたご遺族の心を慰めるための大切な方法です。
供花や弔電は、故人への追悼と遺族へのいたわりの気持ちを形にして伝えるものです。それぞれの意味合いやマナーを理解し、適切な方法でタイミング良く手配することが重要です。
供花は祭壇を飾り、その場を厳かに彩ることで故人の冥福を祈ります。弔電は、遠方にいるなどの理由で参列できない人が、お悔やみのメッセージを届けることができます。どちらも、形は違えど、故人と遺族に寄り添う気持ちを表すための大切な手段となります。
供花(きょうか・くげ)について
供花とは、故人の霊前に供えるお花のことです。祭壇の両脇などに飾られます。
目的・意味:
- 祭壇や会場を飾り、故人の霊を慰める。
- 故人の冥福を祈る気持ちを表す。
- 遺族の悲しみを慰める。
手配方法:
- 葬儀社に依頼する: 訃報の連絡を受けた際に、担当している葬儀社を確認し、直接依頼するのが最も確実でスムーズです。会場の雰囲気や他の供花とのバランス、設置場所などを考慮して、適切なものを用意してくれます。
- 自分で花屋に手配する: 懇意にしている花屋や、インターネットの供花手配サービスを利用する方法もあります。その場合は、以下の点に注意が必要です。
- 斎場名、葬儀の日時(通夜または告別式)、喪家名、喪主名を正確に伝えること。
- 供花の持ち込みが可能か、また特定の業者が指定されていないかを、事前に葬儀社や斎場に確認すること。(持ち込み料がかかる場合や、指定業者以外不可の場合もあります)
自分で花屋を手配する際の注意点! 必ず事前に斎場へ「供花の持ち込み可否」「指定業者の有無」を確認しましょう。確認せずに手配すると、受け付けてもらえない可能性もあります。
種類と色:
- 一般的には、菊、百合、カーネーション、胡蝶蘭などがよく用いられます。
- 色は白を基調とするのが基本ですが、最近では故人の好きだった花や、紫、ピンク、水色、黄色などの淡い色を差し色として加えることも増えています。ただし、あまりに華美にならないよう配慮が必要です。
- トゲのある花(バラなど)や、香りが強すぎる花は避けるのが一般的です。迷った場合は、白基調のオーソドックスなものを選ぶのが無難です。
供花は白基調が基本。菊、百合、胡蝶蘭などが一般的です。トゲのある花や香りの強い花は避けましょう。迷ったら白中心の落ち着いたアレンジメントが無難です。
費用相場:
- 供花は通常「1基(き)」という単位で数え、1基あたり1万5千円~3万円程度 が一般的な相場です。
- 祭壇の両脇に対で飾るため、「一対(いっつい)=2基」で送ることもあります。
札名(ふだな)の書き方:
- 誰からの供花かを示すための名札です。通常、花屋や葬儀社が用意してくれます。
- 個人で送る場合: 氏名のみを記載します。(例:「山田 太郎」)
- 夫婦で送る場合: 連名で記載します。(例:「山田 太郎」「山田 花子」または「山田 太郎・花子」)名字は一つでも可。
- 会社として送る場合: 正式な会社名と、役職名・氏名を記載します。(例:「〇〇株式会社 代表取締役 山田 太郎」)
- 部署やグループで送る場合: 会社名と部署名などを記載し、「〇〇一同」とします。(例:「〇〇株式会社 営業部一同」)
- 友人一同などで送る場合: 「友人一同」などと記載し、全員の氏名を書いた紙を別途添えるのが丁寧です。
手配のタイミング:
- 可能であれば、お通夜に間に合うように手配する のが一般的です。遅くとも、葬儀・告別式の開始数時間前 には会場に届くように手配しましょう。直前すぎると設置が間に合わない可能性があります。
供花の手配はお早めに! お通夜に間に合わせるのが理想ですが、遅くとも葬儀・告別式の開始数時間前には届くように手配しましょう。
供花辞退の場合:






近年、遺族の意向により、香典だけでなく供花も辞退されるケースがあります。訃報の連絡や案内状に「御供花御供物の儀は固くご辞退申し上げます」といった記載がある場合は、遺族の意向を尊重し、供花を送るのは控えましょう。
弔電(ちょうでん)について
弔電は、通夜や葬儀・告別式に参列できない場合に、お悔やみの気持ちを電報で伝えるものです。
目的・意味:
- 遠方や都合で参列できない場合に、故人への追悼の意と遺族へのお悔やみの気持ちを伝える。
- 葬儀・告別式中に読み上げられることで、故人との関係性や弔意を他の参列者にも示す。
手配方法:






文例:
- 定型文を使うのが一般的で、失礼がありません。
- 例:「●●(故人名)様のご逝去の報に接し、心よりお悔やみ申し上げます。」
- 例:「御尊父(ごそんぷ)様のご訃報に接し、謹んで哀悼の意を表します。ご遺族の皆様のお悲しみ、いかばかりかとお察しいたします。安らかなるご永眠を心よりお祈り申し上げます。」
- 例:「ご生前の笑顔ばかりが目に浮かびます。どうぞ安らかにお眠りください。」
忌み言葉(重ね言葉、直接的な死の表現など)は避けるように注意しましょう。インターネットサービスの文例集は、この点が配慮されていることが多いです。
故人との思い出や人柄に触れる一文を加えると、より心のこもった弔電になりますが、長文にならないよう簡潔にまとめます。
手配のタイミング:
- 弔電は葬儀・告別式で読み上げられることが多いため、式の開始前には必ず届いている必要 があります。できれば、葬儀・告別式の前日まで に届くように手配するのが理想的です。
弔電は式開始前に必着! 葬儀・告別式で読み上げられるため、遅くとも式の開始時間までには必ず届くように、余裕をもって手配しましょう。
- 宛名・送り先:
- 宛名: 喪主(もしゅ)の氏名 宛てに送るのが正式です。喪主名が不明な場合は、「〇〇(故人のフルネーム)様 ご遺族様」としても届きます。
- 送り先: 葬儀が執り行われる 斎場や葬儀場の住所 に送ります。自宅で葬儀を行う場合は、自宅の住所宛てです。斎場名も正確に記載しましょう。
- 差出人: 自分の氏名 と、遺族が誰からの弔電か分かるように、住所や連絡先、会社名・部署名・役職名、故人との関係性(例:〇〇大学 同級生)などを明記 しましょう。連名で送ることも可能です。
弔電の宛先・差出人ポイント 宛名は喪主名(不明なら故人名+ご遺族様)、送り先は斎場へ。差出人には、誰からか分かるよう関係性も記載すると丁寧です。
供花や弔電は、参列できない場合でも故人を偲び、遺族に弔意を伝えるための大切な方法です。手配方法やマナー、タイミングを確認し、心を込めて送りましょう。
最優先はご遺族の意向! 供花や弔電も、ご遺族が辞退されている場合は送付を控えましょう。訃報の連絡をよく確認することが大切です。
ただし、遺族が辞退されている場合は、その意向を尊重することが最も重要です。



6. 【葬儀の費用について】相場・内訳・抑えるポイント


葬儀を執り行うにあたり、多くの方が気になるのが「費用」の問題ではないでしょうか。大切な方を送る儀式ですが、現実的に大きな負担となり得るため、事前に知識を得ておくことは非常に重要です。
【結論】葬儀費用は高額だが、内訳を理解し、事前準備や比較検討で管理可能。公的補助も活用を。
まず結論として、葬儀費用は決して安くはありません。
しかし、何に費用がかかっているのか(内訳)をきちんと理解し、事前に情報収集や比較検討を行うことで、ご自身の希望や予算に合わせて費用を管理することは十分に可能です。
利用できる公的な補助制度もありますので、積極的に活用しましょう。
葬儀費用の平均相場(目安)






葬儀費用は、地域や葬儀の形式、規模、内容によって大きく変動しますが、一般的な目安は以下の通りです。
- 全国平均総額: 100万円~200万円程度 が一つの目安とされています。(※あくまで平均であり、近年は小規模化・簡素化により、これより低いケースも増えています。)
- 形式別目安:
- 一般葬: 150万円~
- 家族葬: 80万円~120万円程度
- 一日葬: 40万円~70万円程度
- 直葬(火葬式): 20万円~40万円程度
葬儀費用の相場は100万~200万円が目安ですが、形式によって大きく異なります。家族葬なら80万~、直葬なら20万~など、選択肢によって費用感は変わります。
これらの金額はあくまで参考値です。ご自身の状況や希望に合わせて、具体的な見積もりを取ることが重要です。
葬儀費用の主な内訳






葬儀費用は、主に以下の3つの項目に分けられます。
葬儀費用の主な内訳とポイント
葬儀一式費用
【内容】葬儀社へ支払う費用
- ご遺体の搬送・安置、ドライアイス
- 棺、骨壷、祭壇設営、会場使用料
- 式典進行の人件費、手続き代行費など
Point
- 葬儀社でプラン内容・料金設定が大きく異なる。
- 見積もりをよく確認し、含まれる/含まれないサービスを把握。
飲食接待費用
【内容】飲食・返礼品業者へ
- 通夜振る舞いや精進落としの飲食代
- 会葬者への返礼品(会葬御礼、香典返し)
Point
- 参列者の人数によって大きく変動する。
- 人数を予測し、適切な量やグレードを選ぶことで調整可能。
寺院費用
【内容】宗教者へのお礼
- お布施(読経、戒名/法名などに対して)
- 御車代(交通費)
- 御膳料(会食に同席されない場合)など
Point
- お布施は決まった金額がないことが多い。
- 直接お寺に確認するか、葬儀社に相談するのが一般的。
- 菩提寺がない場合は、葬儀社に紹介してもらうことも可能。
葬儀費用の内訳は主に「①葬儀一式費用」「②飲食接待費用」「③寺院費用」の3つ。特に①は葬儀社によって差が出やすい部分です。
葬儀費用を抑えるポイント






葬儀費用は決して安くありませんが、以下のポイントを押さえることで、負担を軽減できる可能性があります。
葬儀費用を抑えるための5つのポイント
Point 1事前相談・見積もり比較
- 最も重要!可能なら生前に複数社相談&見積もり取得を。
- 同じ内容でも費用が大きく変わることもあります。
- 慌てて1社に決めず、比較検討しましょう。
Point 2葬儀プランの検討
- セットプラン内容をよく確認しましょう。
- 本当に必要なサービスか、不要なオプションはないか吟味。
- 不要なものは外せるか相談してみるのも有効です。
Point 3葬儀形式の選択
- 葬儀形式によって費用は大きく異なります。
- 家族葬、一日葬、直葬(火葬式)など小規模な形式も検討。
- 故人や遺族の意向、規模を考慮して選びましょう。
Point 4公的補助制度の活用
- 葬祭費や埋葬料などが支給される制度があります。必ず申請を!
- **国保・後期高齢者医療制度:**
- 「葬祭費」3~7万円程度 (自治体による)
- 申請先:市区町村役場
- **社会保険 (健保等):**
- 「埋葬料」等 一律5万円
- 申請先:健康保険組合や協会けんぽ等
Point 5互助会・保険の確認
- 葬儀費用に備える互助会に加入している場合。
- 葬儀保険に加入している場合。
- 利用できる内容や給付金を確認しましょう。






追加費用にも注意






最初の見積もり金額だけで安心していると、後から追加費用が発生して驚くことがあります。特に注意したいのは以下のようなケースです。
追加費用が発生しやすいケース
安置日数が延びた場合
- ドライアイス代や安置施設の利用料が、日数に応じて追加でかかることがあります。
飲食・返礼品が想定より増えた場合
- 参列者の人数が予想よりも多かった場合などに、飲食代や返礼品の費用が増加します。
プラン外のオプションを追加した場合
- 見積もりに含まれていないサービス(例:特別な棺、エンバーミング処置など)を追加すると費用がかかります。
支払い方法とタイミング






葬儀費用の支払い方法とタイミングは、葬儀社によって異なりますが、一般的には以下のケースが多いです。
タイミング: 葬儀が終わってから数日~1週間以内に支払うのが一般的です。
支払い方法:
- 現金払い
- 銀行振込
- クレジットカード払い(対応している葬儀社が増えています)
- 葬儀ローン(提携している信販会社のローンを利用できる場合があります)
支払い方法・タイミングの確認も忘れずに。 葬儀後すぐにまとまった金額が必要になることが多いです。クレジットカードやローンが使えるかも含め、事前に確認しておきましょう。
葬儀費用は、形式や内容によって大きく変動しますが、決して安価なものではありません。しかし、費用の内訳をしっかり理解し、事前に複数の葬儀社から見積もりを取って比較検討することで、納得のいく費用で故人をお見送りすることは可能です。
特に、以下のポイントを意識しましょう。
- 慌てず、複数の葬儀社を比較する(事前相談が理想)
- プラン内容をよく確認し、不要なものは見直す
- 家族葬や直葬など、形式を検討する
- 公的な補助金(葬祭費・埋葬料)を忘れずに申請する
- 追加費用が発生するケースを把握しておく
葬儀費用の不安を解消するには、事前の情報収集と比較検討がカギ。そして、利用できる公的補助は必ず活用しましょう。
葬儀は故人との最後の大切なお別れの儀式です。費用に関する不安を少しでも減らし、心ゆくまでお見送りに集中できるよう、この記事がお役に立てれば幸いです。
何から始めればいいか分からない場合は、まずは信頼できそうな葬儀社に事前相談をしてみることから始めてみてはいかがでしょうか。
7. 【挨拶について】喪主・親族・参列者・弔辞のポイントと例文
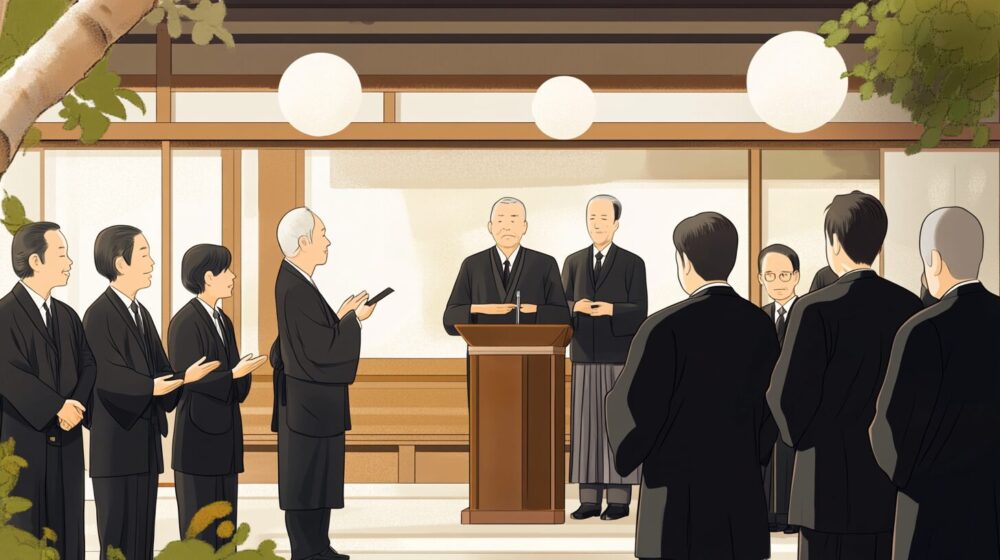
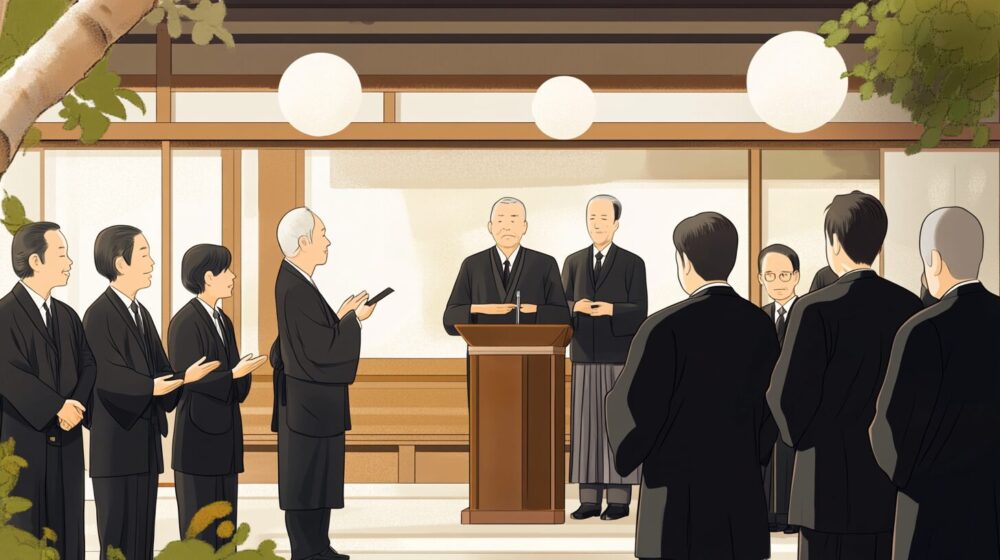
葬儀における挨拶は、故人を偲び、遺族や参列者が互いに気持ちを伝え合うための重要なコミュニケーションです。それぞれの立場や場面に応じて、心を込めた適切な挨拶をすることが求められます。
葬儀の挨拶は、故人への追悼、参列者への感謝、遺族への弔意などを伝える大切な役割を担っています。場面や立場にふさわしい言葉を選び、マナーを守って、誠実な気持ちを伝えることが重要です。



マナーに沿った挨拶は、儀式をスムーズに進め、厳粛な場の雰囲気を保つためにも役立ちます。それぞれの立場での挨拶のポイントを見ていきましょう。
喪主・遺族代表の挨拶
喪主または遺族の代表者は、葬儀の節目で参列者に対して挨拶を行います。悲しみの中、大変な役割ですが、故人に代わって感謝の気持ちを伝える大切な機会です。
目的と心構え:
- 忙しい中、足を運んでくれた弔問客への感謝を伝える。
- 故人が生前お世話になったことへの御礼を述べる。
- (場合により)故人の略歴や人となりなどを簡潔に伝える。
- 今後、遺族を支えてほしいというお願いをする。






ポイント:
- 長さ: 長くなりすぎず、1~3分程度で簡潔にまとめます。
- 忌み言葉: 重ね言葉(たびたび、ますます等)や直接的な生死の表現(死ぬ、生きている頃等)は避けます。
- メモOK: 事前に内容をメモにまとめておき、それを見ながら話しても全く問題ありません。無理に暗記しようとせず、落ち着いて話しましょう。
- 気持ちを込めて: 上手く話そうとするよりも、感謝の気持ちを込めて、自分の言葉で誠実に話すことが最も大切です。
喪主挨拶の心得 ①感謝 ②簡潔(1~3分) ③忌み言葉NG ④メモOK ⑤誠意を込めて
挨拶を行う主なタイミングと例文:
① 通夜終了時(通夜振る舞いの前など)の例文
「本日はご多忙中のところ、〇〇(故人名)のためにお越しいただき、誠にありがとうございます。
故人もさぞ喜んでいることと存じます。(もし可能なら故人の簡単なエピソードや人柄に触れる)。
なお、明日の葬儀・告別式は、〇時より〇〇(場所)にて執り行います。
ささやかではございますが、別室にお食事の席をご用意いたしました。故人の思い出話などお聞かせいただければ幸いです。
どうぞ、ごゆっくりおくつろぎください。本日は誠にありがとうございました。」
② 告別式終了時(出棺前)の例文
「遺族を代表いたしまして、皆様に一言ご挨拶申し上げます。
本日はご多忙中にもかかわらず、〇〇(故人名)の葬儀・告別式にご会葬、ご焼香を賜り、誠にありがとうございました。(故人の略歴や人柄、生前のエピソードなどに簡潔に触れる)。
生前、皆様から寄せられましたご厚情に、故人に代わりまして心より御礼申し上げます。
残された私ども遺族にも、今後とも変わらぬご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
皆様には大変お世話になりました。誠にありがとうございました。」
(この後、霊柩車への移動を促す言葉が続くことが多い)
③ 精進落とし開始時の例文
「皆様、本日は誠にありがとうございました。おかげさまをもちまして、〇〇(故人名)の葬儀・告別式も滞りなく終えることができました。
これもひとえに皆様のお力添えの賜物と、心より感謝申し上げます。
ささやかではございますが、皆様への感謝と慰労の意を込めまして、精進落としの席をご用意いたしました。
故人の思い出話などを語りながら、おくつろぎいただければと存じます。どうぞ、召し上がってください。」
④ 精進落とし終了時の例文
「皆様、本日は長時間にわたり、誠にありがとうございました。
なごりは尽きませんが、これにてお開きの時間とさせていただきます。(納骨や今後の法要の予定が決まっていれば、ここで伝える)。
今後とも、私ども遺族に変わらぬご厚誼を賜りますようお願い申し上げます。本日は誠にありがとうございました。
お気をつけてお帰りください。」
親族代表の挨拶
喪主が高齢であったり、体調が悪かったり、あるいは年少であったりする場合など、喪主に代わって他の親族が挨拶をすることがあります。
その場合も、挨拶の内容は上記の喪主の挨拶に準じます。
挨拶の冒頭で「喪主〇〇に代わりまして、親族を代表し、一言ご挨拶申し上げます」のように述べると良いでしょう。
参列者の挨拶(お悔やみの言葉)
参列者は、遺族に対してお悔やみの言葉を伝えます。
- 目的と心構え: 遺族の悲しみに寄り添い、弔意を伝えることが目的です。長々と話さず、簡潔に、心を込めて伝えることが大切です。
- タイミング: 受付での記帳時、会場内で遺族と顔を合わせた時など。






基本的な言葉:
- 「この度は誠にご愁傷様(しゅうしょうさま)でございます。」
- 「心よりお悔やみ申し上げます。」
- 「突然のことで、まだ信じられません。お力落としのことと存じますが、どうぞご無理なさらないでください。」
- 「安らかなお眠りをお祈りしております。」
注意点:
- 忌み言葉 は避けます。(例:「たびたび」「くれぐれも」「死ぬ」「生きる」など)
- 死因を尋ねる など、遺族の心情を逆なでするような質問は絶対にしません。
- 「頑張って」「元気を出して」といった安易な励ましは控えます。
- 受付や焼香で混雑している場合などは、長話にならないように配慮します。目礼だけでも弔意は伝わります。
弔辞(ちょうじ)
弔辞は、故人への追悼のメッセージであり、告別式中に読み上げられます。
- 目的: 故人の功績や人となりを讃え、生前の思い出を語り、別れを惜しむ気持ちを伝えます。
- 誰が読むか: 故人と特に親しかった友人、恩師、仕事関係者などが、遺族から依頼されて読みます。勝手に申し出るものではありません。






依頼された場合のポイント:
- 長さ: 3分程度(文字数にして1000字前後) が目安です。
- 内容: 故人との出会いや印象的なエピソード、故人の人柄が偲ばれる話、故人への感謝の気持ち、そして別れの言葉などを盛り込みます。個人的な感傷に偏りすぎず、参列者にも故人の素晴らしさが伝わるように構成します。
- 構成例:
- 呼びかけ: 「〇〇(故人名)さん」「〇〇君」など、生前の呼び方で語りかける。
- 訃報に接した驚きや悲しみ: 突然の知らせへの正直な気持ちを述べる。
- 故人との思い出: 具体的なエピソードを交えながら、故人との関係性や印象を語る。
- 故人の人柄や功績: 故人の素晴らしさや社会的な貢献などを讃える。
- 遺族への慰めの言葉: 残された遺族へのいたわりの気持ちを述べる。
- 別れの言葉(結び): 安らかな眠りを祈る言葉や、感謝の言葉で結ぶ。
- 忌み言葉: 弔辞でも忌み言葉は避けるように注意します。
- 読み方: ゆっくりと、落ち着いたトーンで、参列者にも聞き取りやすいように読み上げます。感情的になりすぎないように注意しましょう。(便箋や巻紙に書いたものを読み上げます)
- 事前確認: 可能であれば、原稿が完成したら、事前に遺族に内容を確認してもらうと、より丁寧で安心です。
葬儀における挨拶は、形式的なものと捉えず、それぞれの立場から心を込めて行うことが大切です。マナーを守りつつ、故人への想いや感謝、遺族へのいたわりの気持ちを、自分の言葉で誠実に伝えましょう。
まとめ:心を込めて故人を見送るために


この記事では、葬儀の基本的な流れから、服装・香典・焼香などの具体的なマナー、供花・弔電の手配、費用の相場、そして挨拶のポイントまで、葬儀に関する様々な情報を網羅的に解説してきました。



様々な作法やしきたりがありますが、葬儀において最も大切なことは、形式的なマナーを完璧にこなすこと以上に、故人を敬い、心からその冥福を祈る気持ちです。
そして、深い悲しみの中にいるご遺族の気持ちに寄り添い、思いやりを持って接することです。
葬儀で一番大切な心構え
- 故人を敬い、冥福を祈る心
- ご遺族の悲しみに寄り添う心
服装を整え、香典を用意し、マナーを守って焼香を行う…これら一つ一つの作法は、そうした目に見えない「弔意」や「いたわり」の心を形として表すためのものなのです。
突然の訃報は、誰にとっても動揺し、不安になるものです。しかし、この記事でお伝えした基本的な知識が、あなたの心構えとなり、少しでも落ち着いて故人との最後のお別れに臨むための一助となれば、これほど嬉しいことはありません。
もし作法に迷うことがあっても、過度に心配する必要はありません。周りの方の動きを参考にしたり、葬儀社のスタッフにそっと尋ねたりすれば大丈夫です。



この記事が、あなたが大切な方を敬意と思いやりをもって見送るための一助となることを、心より願っております。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。故人の安らかな眠りと、ご遺族の皆様の悲しみが少しでも和らぐことをお祈り申し上げます。
葬儀・告別式 持ち物チェックリスト(一般参列者向け)
いざという時に慌てないよう、葬儀・告別式に参列する際に必要な持ち物をリストアップしました。事前に確認し、忘れ物がないように準備しましょう。
◆ 必ず持っていくもの(必須) ◆
- □ 香典
- 金額は事前に相場を確認し、新札は避けて用意する。
- 香典袋(不祝儀袋)に宗教・宗派に合った表書きと自分の氏名を書く。
- 中袋(または中包み)に金額(旧漢字推奨)と住所・氏名を書く。
- 袱紗(ふくさ)に包んで持参する。
- □ 袱紗(ふくさ)
- 香典を包むための布。弔事には紫、紺、深緑、グレーなどの寒色系を使用(紫は慶弔両用)。
- 左開きになるように香典を包む。
- □ 数珠(じゅず)
- 仏式の葬儀の場合に持参。自分の宗派のものがあればベスト。
- 無理に用意する必要はないが、持っているなら忘れずに。貸し借りはマナー違反。
- □ ハンカチ
- 白無地 または 黒無地 のシンプルなもの。
- レースの縁取り程度なら可。色柄物やタオル地のものは避ける。
- □ 携帯電話・スマートフォン
- 会場に到着したら、必ずマナーモードにするか電源を切る。
- □ 小さめのバッグ(主に女性)
- 黒の布製 が最もフォーマル。光沢や金具、装飾が控えめな革製も可。
- 大きな荷物はクロークなどに預け、会場内には必要最低限のものが入るバッグで。
- □ 財布
- 必要最低限の現金、交通系ICカード、クレジットカードなどを。
- バッグに入る大きさか確認。
◆ 身だしなみに関するもの ◆
- □ 黒のフォーマルな服装(準喪服)
- 男性:ブラックスーツ、白無地ワイシャツ、黒無地ネクタイ
- 女性:ブラックフォーマル(ワンピース、アンサンブルなど)
- □ 黒の靴
- 男性:光沢控えめの黒い革靴(ストレートチップ or プレーントゥ)。
- 女性:光沢や装飾のない黒いパンプス(布製 or 革製、ヒールは高すぎないもの)。
- □ 黒の靴下(男性) / 黒のストッキング(女性)
- 男性:黒無地。
- 女性:黒の薄手(30デニール以下目安)、無地。予備も持っておくと安心。
- □ ティッシュペーパー
- ポケットティッシュ。できればシンプルなケースに入れる。
◆ あると便利なもの・状況に応じて必要なもの ◆
- □ コート・上着(寒い時期)
- 黒、濃紺、濃いグレーなど地味な色でシンプルなデザインのもの。
- 会場に入る前に脱ぐのがマナー。
- □ 黒い傘(雨天時)
- 黒や紺などの地味な色の傘が望ましい。派手な色柄は避ける。
- □ メガネ
- 普段コンタクトレンズの方も、涙で外れる可能性を考えメガネが良い場合も。派手なフレームは避ける。
- □ 常備薬
- 普段服用している薬がある方は忘れずに。
- □ 名刺
- 仕事関係の葬儀の場合、受付で記帳の代わりに提出することがある。
- □ (乳幼児連れの場合 ※推奨はしません)
- おむつ、おしりふき、ミルク、着替え、音の出ないおもちゃなど。
- 葬儀の場に乳幼児を連れて行くかは慎重に判断し、他の参列者への配慮を忘れずに。

