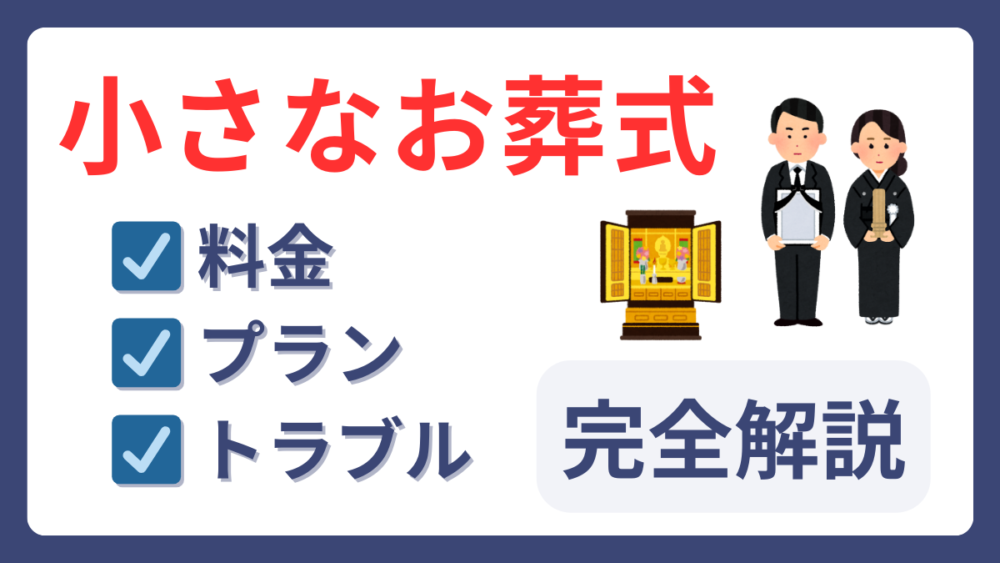- 「急なことで、お葬式の準備をどう進めたらいいか分からない…」
- 「葬儀費用はできるだけ抑えたいけど、どんな選択肢があるの?」
- 「小さなお葬式ってよく聞くけど、実際のプラン内容や評判はどうなんだろう?」
- 「特に直葬や自宅葬、祭壇やお坊さんの手配について詳しく知りたい!」
大切な方とのお別れは突然訪れることも多く、深い悲しみの中で葬儀の準備を進めるのは、精神的にも時間的にも大きな負担となりますよね。
近年、「小さなお葬式」のように費用を抑えたシンプルな葬儀プランが注目されています。
しかし、インターネット上には様々な情報が溢れており、「結局どのプランが自分たちに合っているの?」「直葬や自宅葬って具体的に何をするの?」「祭壇やお坊さんは必須?費用は?」といった疑問や、追加費用が発生しないかという不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
私自身、これまで葬儀に関する様々なご相談をお受けする中で、費用やプラン選び、祭壇の準備やお坊さんの手配などで悩む多くの方々を見てきました。
その経験から、皆さまの不安な気持ちに寄り添い、客観的で分かりやすい情報をお届けすることを常に心がけています。
そこでこの記事では、全国対応で低価格な葬儀プランを提供し、累計52万件以上の葬儀実績(※)を持つ「小さなお葬式」について、その仕組みや特徴から、特にニーズの高い「直葬(火葬式)プラン」と「自宅葬プラン」(対応状況含む)を中心に、気になる祭壇の種類やお坊さん(寺院)手配の費用まで、網羅的に、そして分かりやすく解説します。(※件数は変動する可能性があるため、最新情報は公式サイト等でご確認ください)
この記事を最後まで読めば、「小さなお葬式」の各プランの内容や費用感が明確になり、祭壇やお坊さんの手配に関する疑問も解消されます。
メリットだけでなく、注意すべき点(デメリット)も理解した上で、あなたのご状況や故人様への想いに最も合った後悔しないプランを見つけることができるでしょう。
費用を抑えながらも、心を込めて故人様をお見送りするために。この記事が、あなたにとって最適な「小さなお葬式」のプランを見つけるための一助となれば幸いです。ぜひ最後までご覧ください。
小さなお葬式とは?全国対応の低価格プランが選ばれる理由と仕組み

「小さなお葬式」は、2009年のサービス開始以来、累計52万件以上(※)という豊富な葬儀実績を持つ、低価格プランに特化した葬儀サービスです。
顧客満足度も96%(自社調査)と高く、全国の葬儀受注件数で8年連続No.1を獲得(2023年 TPCマーケティングリサーチ調べ ※)するなど、多くの方に選ばれています。
(※実績・順位に関する情報は調査時期により変動する可能性があります。最新情報は公式サイト等でご確認ください。)
 新米くん
新米くん


なぜ「小さなお葬式」は低価格を実現できるのか?その仕組みを解説
「小さなお葬式」が従来の葬儀費用に比べて低価格を実現できる背景には、独自の仕組みがあります。
必要なものだけ選べるシンプルなプランで、
無駄な費用をカットしています。
全国の提携式場の空き時間を活用し、
場所代などの固定費を抑えています。
家族葬など小規模なお葬式に特化し、
運営を効率化してコストを削減。
ネットで情報を伝え集客することで、
広告費や人件費を抑えています。
【ビジネスモデルの注意点】 この低価格モデルは、「小さなお葬式」が葬儀の依頼を受け付け、それを提携する地元の葬儀社が「小さなお葬式」の価格設定で施行し、「小さなお葬式」が仲介手数料を得るというプラットフォーム型(仲介型)の仕組みに基づいています。
利用者にとっては明確な価格でサービスを受けられるメリットがある一方で、以下の点に注意が必要です。
基本プランは最低限。
要望次第でオプション費用がかさむ可能性や、
追加を勧められる場合があります。
サービスは提携葬儀社が提供します。
担当する会社によって
対応や質に差が出ることがあります。
利用を検討する際は、基本プランの内容と、追加料金が発生する可能性のある項目を事前にしっかり確認することが、トラブルを避けるために非常に重要です。
全国の対応エリアと提携斎場について
「小さなお葬式」の大きな特徴の一つは、その広範な対応エリアです。一部の離島や山間部を除き、日本全国47都道府県でサービスを提供しています。
これは、全国に4,000ヶ所以上(あるいは5,000ヶ所以上)の提携斎場・葬儀場ネットワークと、1,100社以上の提携葬儀社(実際に施行を担当する会社)を持っているためです。
利用者は、公式サイトの「葬儀場を探す」ページから、都道府県や市区町村、あるいは郵便番号や施設名といったフリーワードで、近くの対応可能な斎場を簡単に検索できます。
全国どこでも、基本的に同じプラン内容・価格でサービスが提供されることを目指しています。 旅先での急な不幸など、予期せぬ場所でも対応可能な点は大きな強みです。
【提携斎場利用の注意点】
担当する葬儀社は通常選べません。
依頼後に決まる点に留意しましょう。
地域によって提携先の数や選択肢が異なります。
事前の確認がおすすめです。
遠方の斎場の場合、規定距離超過分の
追加搬送費が発生することがあります。



24時間365日対応!万全のサポート体制
「小さなお葬式」は、もしもの時に備え、24時間365日対応のサポート体制を整えています。
深夜・早朝、土日祝日を問わず、専門のコールセンタースタッフがフリーダイヤルで常時待機しており、葬儀に関するあらゆる相談や依頼に対応します。
【コールセンターで相談できること】
状況や希望に合わせて
最適なプラン選びをサポートします。
見積もり内容や追加料金の可能性など
費用について説明します。
ご希望エリアで利用できる
斎場の情報を案内します。
何から始めればよいか、
葬儀全体の流れや手順を説明します。
死亡届など
手続きに必要な書類について説明します。
葬儀に関するあらゆる疑問や不安に
丁寧にお答えします。
特に、危篤や逝去直後の緊急時には、電話での連絡が最も迅速な対応につながります。経験豊富なスタッフが状況を伺い、ご遺体の搬送手配から今後の流れまで、丁寧にご案内します。






この迅速で丁寧な電話対応は多くの利用者から高く評価されていますが、一部には時間帯によって繋がりにくかった、担当者が変わって連携不足を感じた、という声も稀に見られます。
とはいえ、全体として、いつでも専門家に相談できる体制は大きな強みと言えるでしょう。
【小さなお葬式の直葬プラン】火葬式の内容と費用をわかりやすく解説


「小さなお葬式」が提供するプランの中でも、最もシンプルな形式の一つが「小さな火葬式」と呼ばれる直葬プランです。
ここでは、まず一般的な直葬(火葬式)の概要を説明し、その上で「小さなお葬式」のプラン内容、費用、注意点などを詳しく見ていきます。
そもそも直葬(火葬式)とは?流れと特徴を解説
直葬(ちょくそう)、または火葬式(かそうしき)とは、お通夜や葬儀・告別式といった宗教的な儀式を基本的に行わず、故人のご遺体を火葬することを中心とした、最もシンプルな葬送の形式です。
通夜・告別式を行わないため、
時間的・経済的な負担が大幅に軽減されます。
参列者は家族やごく親しい友人など、
数名に限定されることが一般的です。
儀式や会場設営が不要なため、
葬儀費用を大幅に抑えられます。
(一般的な直葬の費用相場は
20万円~50万円程度)
親しい人だけで故人を見送るため、気兼ねなく、
静かにお別れの時間を過ごせます。
【一般的な流れ】
病院などから安置場所へ
ご遺体を搬送します。
法律により最低24時間、
ご遺体を安置します。
故人様を棺に
納めます。
ご安置場所から
火葬場へ向かいます。
炉前で最後のお別れ後、
火葬します。
(希望により炉前読経も)
ご遺骨を骨壺に
収めます。






【直葬の注意点】 儀式を大幅に省略するため、親族や菩提寺の理解が得られない場合があります。特に菩提寺がある場合は、必ず事前に相談しないと納骨を断られるなどのトラブルになる可能性があるので注意が必要です。
小さなお葬式の「小さな火葬式」プランに含まれる内容一覧
「小さなお葬式」の「小さな火葬式」プランは、上記の一般的な直葬(火葬式)の流れに沿った、儀式を行わないシンプルなプランです。
【小さな火葬式プラン 標準内容(例)】 (※最新の情報は必ず公式サイト等でご確認ください)
| カテゴリ | 項目 | 含まれる内容/数量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 搬送 | 寝台車 | 2回(逝去場所→安置場所、安置場所→火葬場)各50kmまで | 超過分は追加料金 |
| 安置 | 安置施設利用料 or 自宅安置 | 3日分 | 自宅安置も可 |
| ご遺体処置 | ドライアイス | 3日分 | 超過分は追加料金 |
| 納棺 | 納棺作業(基本的なもの) | 湯灌・化粧などはオプション | |
| 仏衣一式 | 故人にお着せするもの | ||
| 棺関連 | 棺・棺用布団 | 標準的なもの | |
| 仏具等 | 枕飾り一式 | ご遺体の枕元に飾るもの | |
| 線香・ろうそく | |||
| 白木位牌 | 葬儀用の仮の位牌 | ||
| お別れ用花束 | 棺に入れるお花 | ||
| 手続き | 役所・火葬手続き代行 | 死亡届関連・火葬許可申請など | |
| スタッフ | 運営スタッフ | 搬送・設営・案内など | |
| 火葬後 | 骨壷・骨箱 | 標準的なもの | 種類・グレードアップは要確認/追加料金 |
| 自宅飾り一式(後飾り) | 火葬後、自宅で遺骨を安置するための簡易祭壇 | ||
| プラン外項目 | 火葬料金 | 別途お客様負担 | 地域・火葬場により費用変動(重要) |
| プラン外項目 | 儀式用祭壇 | なし | |
| プラン外項目 | 宗教者費用(お布施等) | なし(オプション) | |
| プラン外項目 | 飲食接待費 | なし(オプション) | |
| プラン外項目 | 遺影写真 | なし(オプション) | |
| プラン外項目 | 付き添い安置 | なし(オプション) |
この表からもわかるように、「小さな火葬式」プランは、直葬に必要な最低限の物品とサービスがパッケージ化されています。
ただし、最も重要な火葬料金は含まれていない点、そして儀式用の祭壇や宗教者への謝礼(お布施)は含まれず、必要であれば別途手配・費用負担となる点を明確に理解しておく必要があります。
【「小さなお別れ葬」プランとの違い】
「小さなお葬式」には、さらに費用を抑えた「小さなお別れ葬」プランもあります。
これは「小さな火葬式」から仏衣、枕飾り、自宅飾り、白木位牌などを省いたプランで、無宗教での火葬のみを想定しています。
お坊さんの手配も不可となっています。ご自身の希望に合わせてどちらのプランが適切か検討しましょう。
直葬プランの総額費用と追加料金が発生するケース
「小さな火葬式」プランの費用について、より具体的に見ていきましょう。
【基本料金(2025年4月現在)】 (※最新の価格は必ず公式サイトでご確認ください)
- 資料請求割引適用後:174,900円(税込)
- 通常価格:209,000円(税抜)
【総額費用の目安】
基本料金に加えて、必ず火葬料金がかかります。
これは地域や利用する火葬場(公営か民営か)によって大きく異なり、数万円~6万円以上かかることもあります。
したがって、「小さな火葬式」の総額費用は、約20万円台前半から20万円台後半が一つの目安となりますが、火葬料金次第で変動します。
【追加料金が発生する主なケース】
「小さなお葬式」は定額プランを謳っていますが、特定の条件下では追加料金が発生します。これは利用者の不満やトラブルの原因ともなり得るため、事前に把握しておくことが極めて重要です。
| 項目 | 目安費用(情報源により変動あり) | 備考 |
| 火葬料金 | 数万円~6万円以上 | プラン外・必須 |
| 規定日数超過の安置料(3日超過分) | 1日あたり 5,000円~22,000円 | 火葬場の空き状況等で日数超過時に発生 |
| 規定日数超過のドライアイス料(3日超過分) | 1日あたり 5,000円~15,000円 | 安置日数超過に伴い発生 |
| 付き添い安置 | 1日あたり 55,000円(例) | 故人に付き添って安置施設に宿泊する場合 |
| 搬送距離超過(1回50km超過分) | 10km毎 5,500円(例) | 遠方への搬送が必要な場合 |
| 宗教者費用(お布施・戒名料) | 80,000円~(小さなお葬式手配) | オプションで依頼する場合 |
| オプション品の追加 | 個別見積もり | 例:遺影写真、湯灌、グレードの高い棺、霊柩車など |
| 特定の式場利用料 | 個別見積もり | プラン規定を超える利用料の式場を使う場合(主に他のプラン) |
| 深夜・早朝料金、休日料金 | 個別見積もり | 搬送や対応時間帯による可能性 |
| 警察案件等の特殊対応 | 個別見積もり | 検案料や特別な処置が必要な場合 |
(※上記費用はあくまで目安であり、状況や地域によって変動します。最新情報は必ずご確認ください。)
特に注意が必要なのは、安置日数とドライアイスの日数です。 火葬場の予約状況によっては、想定よりも安置期間が長引き、追加料金が発生することがあります。
過去には「追加料金一切不要」との広告表示が問題となり、消費者庁から措置命令を受けた経緯もあります(2017年)。
現在は例外規定が明記されるようになっていますが、利用者は契約前に、基本プランの内容、含まれないもの、そして追加料金が発生しうる条件について、担当者から詳細な説明を受け、見積書を細部まで確認することが、後々のトラブルを避けるために不可欠です。
直葬(火葬式)の場合、祭壇は用意される?
結論から言うと、「小さなお葬式」の「小さな火葬式」プランには、儀式用の祭壇(さいだん)は含まれていません。
これは、通夜や告別式といった儀式を行わない直葬の特性に合わせたものであり、祭壇を省略することで費用を抑えるというプランの趣旨に沿ったものです。
同様に、さらにシンプルな「小さなお別れ葬」プランにも祭壇は含まれません。
ただし、火葬後に自宅でご遺骨を安置するための「自宅飾り一式(後飾り祭壇)」は、「小さな火葬式」プランに含まれています。
これは、四十九日法要までの間など、ご遺骨、白木位牌、遺影などを一時的に安置し、お線香をあげられるようにするための簡易的な祭壇です。
この後飾り祭壇が含まれていることで、火葬が終わって自宅に戻った後も、故人を偲ぶための最低限の設えが整うことになります。
また、棺の中に故人と一緒に入れるための「お別れ用花束(別れ花)」もプランに含まれています。
したがって、直葬(火葬式)プランでは、葬儀会場に飾られるような大きな祭壇はありませんが、火葬後の自宅での安置に必要な簡易祭壇と、最後のお別れのためのお花は用意される、と理解しておくとよいでしょう。



【小さなお葬式の自宅葬プラン】住み慣れた家で見送る温かい選択肢


住み慣れた自宅で、家族や親しい人たちだけで故人を送る「自宅葬」は、温かく、プライベートな雰囲気の中で最期のお別れができる選択肢として、関心を持つ方もいるでしょう。
ここでは、まず一般的な自宅葬のメリット・デメリット、そして「小さなお葬式」で自宅葬を行う場合の可能性や注意点について解説します。
自宅葬のメリット・デメリットとは?後悔しないためのポイント
自宅葬には、斎場や葬儀ホールで行う葬儀とは異なる、特有のメリットとデメリットがあります。
住み慣れた自宅で、故人も遺族も
リラックスして過ごせます。
時間に縛られず、ゆっくりお別れできます。
付き添いもしやすいです。
斎場の利用料がかからず、
費用を抑えられる可能性があります。
故人らしいパーソナルな空間を作り、
自由な演出が可能です。
高齢者や体調がすぐれない方も、
移動負担少なく参加できます。
ごく近所の方なら気軽に足を運びやすく、
参列しやすいです。
棺安置、参列者スペース等の確保を。
(目安6畳程度)
人の出入りや音について、
近隣への配慮と事前説明が大切です。
部屋の準備や後片付け、弔問客対応など、
遺族の負担が増えます。
管理規約での禁止や搬送困難な場合も。
賃貸は家主許可を。
準備の手間賃や物品の個別手配で、
費用がかさむことも。






小さなお葬式の自宅葬プランに含まれる内容と当日の流れ
「小さなお葬式」の公式サイトや提供されているプラン一覧を見る限り、「自宅葬プラン」という名称の専用プランは、現時点(2025年4月)では明記されていません。
主力プランは「小さな火葬式」などの直葬形式、または提携斎場を利用する「小さな一日葬」「小さな家族葬」「小さな一般葬」です。
「小さなお葬式」で自宅葬を行う可能性
提携葬儀社による個別対応
「小さなお葬式」は全国の葬儀社と提携しています。
依頼を受けた提携葬儀社が、利用者の希望に応じて自宅での葬儀に対応してくれる可能性があります。
この場合、「小さな家族葬」などの既存プランをベースに、施行場所を自宅としてアレンジする形になるかもしれません。
オプションとしての対応
標準プランにはなくても、特別な要望として自宅での施行を相談できる可能性も考えられます。
いずれにしても、「小さなお葬式」で自宅葬を希望する場合は、必ず事前に電話相談などで「自宅での葬儀を希望している」旨を明確に伝え、対応の可否、可能な場合のプラン内容、費用、流れについて詳細を確認する必要があります。
もし「小さなお葬式」経由で自宅葬が実施可能となった場合の一般的な流れ(葬儀社が関与する場合)は、以下のようになると考えられます。
- ご逝去・搬送・自宅安置
- 打ち合わせ(葬儀社担当者と日程、内容、祭壇、費用などを決定)
- 準備・設営(スペース確保、家具移動、祭壇設置など)
- 納棺
- 通夜(行う場合)
- 葬儀・告別式
- 出棺(火葬場へ)
- 火葬・お骨上げ
- 自宅へ戻る・(必要なら)後飾り設置
- (必要なら)精進落とし
この流れはあくまで一般的なものであり、具体的な内容は選択するプラン(例:「小さな家族葬」を自宅で行うなど)や、提携葬儀社の方針によって変わる可能性があります。
自宅葬プランの費用と事前に確認すべき点(スペース、近隣への配慮など)
前述の通り、「小さなお葬式」には専用の自宅葬プランが明記されていないため、確定的な費用を示すことは困難です。
費用に関する考察
40万円~100万円程度
が目安とされます。
- プラン料金が基本だが、
設営等で追加料金の可能性。 - 斎場費が含まれるプランは、
料金の扱いを確認。 - 自宅だから必ず安価とは限らない。
- 必ず個別に見積もりを!
事前に確認すべき重要事項
自宅葬を検討する際には、以下の点を必ず事前に確認・準備する必要があります。
【自宅葬の事前チェックリスト】
- ✅ スペースの確認:
- 棺の安置場所、祭壇設置場所、参列者スペース、搬出入経路は十分か?
- ✅ 住居の規約・許可:
- マンション等の管理規約はOKか? 賃貸の場合は家主の許可は?
- ✅ 近隣への配慮:
- 事前に挨拶と説明を行い、理解を得る。駐車スペースの確保。音への配慮。
- ✅ 物理的な準備:
- 家具の移動、弔問客対応の準備、出棺中の留守番担当など。
- ✅ 葬儀社との役割分担:
- 誰が何を担当するのか(遺族か、提携葬儀社か)を明確にする。






自宅葬における祭壇の設置と準備について
自宅葬で宗教的な儀式を行う場合や、故人を偲ぶ中心的な場所として、祭壇を設置することが一般的です。
祭壇の種類と準備方法
- 葬儀社による設置: 最も一般的。提携葬儀社が自宅のスペースに合わせて適切な祭壇(白木祭壇、生花祭壇など)を提案・設置します。
- 遺族による準備: 宗教儀礼を行わない場合など、自宅のテーブル等で簡易的な祭壇を作ることも可能。遺影、位牌、花、線香、故人の好きなものなどを飾ります。
- レンタル: 祭壇のみレンタルも可能(費用目安:3万円~)。
【「小さなお葬式」の場合】
もし「小さな家族葬」や「小さな一日葬」プランの応用として自宅葬が行われる場合、これらのプランには標準で生花祭壇が含まれています(一日葬:幅約1.8m/1段、家族葬:幅約2m/2段が例)。そのため、提携葬儀社が自宅に祭壇を設置してくれる可能性が高いと考えられます。
自宅葬での祭壇 確認事項
- 標準祭壇のサイズ確認: プランに含まれる標準祭壇が自宅スペースに収まるか。
- サイズ変更・仕様変更: スペースに合わない場合、小さいものに変更可能か、あるいは祭壇なしになるか。
- 設置場所と作業分担: どこに設置するか、家具移動は誰が行うか。
- 追加費用: 標準からの変更や特別な装飾を希望する場合の追加費用。
自宅という限られた空間での設置になるため、斎場と同じ仕様とは限りません。打ち合わせの際に、自宅の間取りなどを伝え、設置可能な祭壇の仕様と費用について、提携葬儀社の担当者と十分に確認することが重要です。
小さなお葬式の祭壇|プランごとの違いとオプション(花祭壇・後飾り祭壇)


葬儀において祭壇は、故人を偲び、弔いの気持ちを表すための中心的な存在です。「小さなお葬式」では、プランによって祭壇の有無や種類が異なります。
また、より華やかにしたい場合のオプションや、葬儀後に自宅で用いる後飾り祭壇についても知っておく必要があります。
各プランに含まれる基本的な祭壇について
「小さなお葬式」の主要5プランにおける、標準的な祭壇の扱いは以下の通りです。(※仕様は一例であり、最新情報は要確認)
| プラン名 | 祭壇の有無 | 祭壇の種類(標準) | 標準仕様(例) | 備考 |
| 小さなお別れ葬 | なし | – | – | 仏具等も含まない、無宗教・火葬のみ向け |
| 小さな火葬式 | なし | – | – | 儀式用祭壇なし。後飾り祭壇は含む |
| 小さな一日葬 | あり | 生花祭壇 | 幅 約1.8m / 1段 | プランに式場利用料(税込5万円まで)含む |
| 小さな家族葬 | あり | 生花祭壇 | 幅 約2m / 2段 | プランに式場利用料(税込10万円まで)含む |
| 小さな一般葬 | あり | 生花祭壇 | 幅 約2m / 2段(家族葬と同等かそれ以上) | プランに式場利用料(税込10万円まで)含む。アップグレード可 |
このように、火葬のみを目的とした「小さなお別れ葬」「小さな火葬式」プランでは、儀式用の祭壇は用意されません。
一方、告別式を行う「小さな一日葬」、通夜・告別式を行う「小さな家族葬」「小さな一般葬」プランには、標準で生花祭壇が含まれています。






オプションで選べる華やかな花祭壇の種類と費用
「小さな一日葬」「小さな家族葬」「小さな一般葬」プランでは、標準の生花祭壇から、より多くの花を用いた華やかな祭壇へとアップグレードするオプションが用意されています。
【花祭壇アップグレード費用例(目安)】
(基本プラン料金に加算される額。※最新価格要確認)
- シンプル: + 約5.5万円~
- ブロンズ: + 約11万円~
- シルバー: + 約22万円~
- ゴールド: + 約33万円~
- プレミア: + 約55万円~
- プレミアプラス: + 約77万円~
これらの例からもわかるように、祭壇のグレードアップは、基本プランの料金を大幅に上回る追加費用となる可能性があります。最も高価なオプションでは、基本プラン料金に70万円以上が加算される計算になります。
【花祭壇オプション選択のポイント】
- 予算: どこまで費用をかけられるか。
- 故人のイメージ: 好きだった花や色を取り入れたいか。
- 葬儀の規模・雰囲気: 会場とのバランスはどうか。
- 標準祭壇との比較: 標準の内容を確認し、どの程度グレードアップが必要か判断する。






また、実際の祭壇は季節や地域によって使用される花材が異なるため、写真通りのイメージにならない可能性も念頭に置きましょう。
葬儀後の「後飾り祭壇」は必要?準備と意味合い
葬儀・火葬が終わった後、ご遺骨はすぐに墓地などに納骨されるわけではなく、多くの場合、四十九日法要まで自宅で安置されます。
この期間、ご遺骨、白木位牌(仮の位牌)、遺影などを安置し、お線香をあげて供養するための簡易的な祭壇が「後飾り祭壇(あとかざりさいだん)」または「自宅飾り(じたくかざり)」です。
【必要性と意味合い】
法律上の義務ではありませんが、仏教の慣習として、納骨までの間、故人の魂が宿るとされる位牌や遺骨を丁寧に祀るために用いられます。家族が日々手を合わせ、故人を偲ぶための大切な拠り所となります。
【準備方法】
- プランに含まれる場合: 「小さなお葬式」では、「小さな火葬式」「小さな一日葬」「小さな家族葬」「小さな一般葬」プランに「自宅飾り一式(後飾り)」が含まれています。(「小さなお別れ葬」には含まれません)この場合、提携葬儀社が準備・設置してくれることが一般的です。
- 別途手配する場合:
- 購入: 仏具店やネットで購入(簡易な段ボール製で1万円程度、一般的なもので3千円~1.5万円程度)。
- レンタル: 葬儀社でレンタル(費用目安:3万円前後)。
- 代用: 自宅の小さなテーブルなどで代用。






祭壇を選ぶ上での注意点と確認事項
葬儀の祭壇を選ぶ際には、後悔しないためにいくつか注意すべき点があります。
【祭壇選びのチェックポイント】
- ✅ プラン内容の確認: 選択プランに祭壇が含まれるか? 標準はどんな種類・規模か?(火葬式は含まれない)
- ✅ 予算の明確化: 花祭壇オプションは高額になる可能性。予算上限を決めて検討する。
- ✅ 会場とのバランス: 祭壇の大きさが会場(斎場 or 自宅)の広さや雰囲気に合っているか?
- ✅ 宗教・宗派の確認: 特定の宗教・宗派に適した形式か?(生花祭壇は比較的宗教を問わない)
- ✅ イメージの共有: 写真だけでなく、使用花材やボリュームを具体的に確認。季節や地域差も考慮。
- ✅ 後飾り祭壇の確認: プランに含まれるか? サイズ・デザインは? 別途手配が必要か?



小さなお葬式のお坊さん手配(寺院手配)|費用相場と注意点を解説


仏式の葬儀を行う場合、お坊さん(僧侶)による読経や戒名の授与が不可欠となることがあります。「小さなお葬式」では、お寺とのお付き合いがない方でも利用できる、お坊さんの手配サービス(寺院手配)を提供しています。ここでは、その必要性、費用、注意点などを解説します。
お坊さん(僧侶)は必ず手配すべき?判断基準と手配の流れ
【手配の必要性】 お坊さんの手配は、法律上の義務ではありません。手配するかどうかは、故人や遺族の信仰、葬儀の形式、そして納骨先の状況によって判断します。
- 必要なケース: 仏式希望、戒名希望、菩提寺の墓地に納骨する場合(最重要)。
- 不要なケース: 無宗教、神式・キリスト教式、宗教儀礼不要、宗教不問の墓地へ納骨。
【判断基準】 最も重要なのは、故人の遺志と遺族の意向です。加えて、納骨先の条件(特に菩提寺の有無)は必ず確認が必要です。
【最重要注意点】菩提寺がある場合 菩提寺があるにも関わらず、相談なしに他の僧侶に依頼したり、無宗教で葬儀を行ったりすると、納骨を拒否されるなどの深刻なトラブルに発展する可能性があります。自己判断は絶対に避けましょう。
【手配の流れ】
- 菩提寺への連絡(最優先): もし菩提寺がある場合は、まず菩提寺に連絡し、葬儀の依頼と相談を行います。
- 菩提寺がない場合:「小さなお葬式」等へ依頼:
- 葬儀プランの打ち合わせ時に「寺院手配」を希望する旨を伝えます。
- 希望する宗派(主要八宗派に対応)、日時・場所などを伝えると、提携寺院から僧侶を手配してくれます。






小さなお葬式で依頼した場合の寺院手配・僧侶手配の費用目安
「小さなお葬式」では、お寺とのお付き合いがない方でも安心して仏式の葬儀を行えるよう、定額での寺院手配サービスを提供しています。
この費用には、通常別途必要となる「お布施」「御車代(交通費)」「御膳料(食事代)」が含まれており、費用の透明性が高いのが特徴です。
【小さなお葬式 寺院手配オプション費用(税込)】 (※基本ランクの戒名料含む。最新価格要確認)
| 葬儀プラン | 主な内容(読経箇所など) | 費用目安 |
| 小さな火葬式 | 炉前読経、戒名授与(基本ランク) | 80,000円~ |
| 小さな一日葬 | 告別式読経、式中初七日、炉前読経、戒名授与(基本ランク) | 110,000円~ |
| 小さな家族葬・一般葬 | 通夜読経、告別式読経、式中初七日、炉前読経、戒名授与(基本ランク) | 200,000円~ |
| 法事・法要 | 各法要の読経 | 60,000円 |
(※小さなお葬式利用者は法事・法要が50,000円になる場合あり)
【一般的なお布施相場との比較】
一般的な葬儀におけるお布施の全国平均は約26万円、家族葬でも10万円~50万円、戒名料を含めると40万~50万円といった情報もあり、地域や寺院、戒名のランクによって大きく変動します。
「小さなお葬式」の定額制は、こうした費用の不透明さや変動リスクを避けたい利用者にとって大きなメリットと言えます。
【注意点】
- このサービスは提携寺院の僧侶が派遣されるもので、特定の寺院や僧侶を指定はできません。
- 菩提寺がある場合は、このサービスを利用する前に必ず菩提寺の許可を得てください。






戒名(法名・法号)をつけてもらう場合の費用と流れ
戒名(浄土真宗では法名、日蓮宗などでは法号とも)は、仏弟子となった証として授けられる名前で、仏式の葬儀において重要な意味を持ちます。
【費用】
- 伝統的な相場:戒名の費用(戒名料)は、授かる戒名のランク(位)によって大きく異なります。
- 信士・信女: 10万円~50万円程度
- 居士・大姉: 50万円~80万円程度
- 院号: 100万円を超えることも (※宗派や地域、寺院により差があります)
- 「小さなお葬式」の場合:
- 前述の寺院手配プラン(8万円、11万円、20万円)には、基本的なランクの戒名が含まれています。(おそらく「信士・信女」相当と推測されますが要確認)
- より上位の戒名を希望する場合、対応可能か、またその場合の追加費用がいくらになるかは、別途「小さなお葬式」に問い合わせて確認が必要です。標準プランの費用内で上位の戒名を授かることは難しいでしょう。
【流れ】
- 僧侶への依頼: 葬儀を依頼する僧侶(菩提寺または手配された僧侶)に戒名の授与をお願いします。
- ランクの相談: 遺族は、故人の人となりや予算、先祖の戒名などを考慮し、僧侶と相談してランクを決めます。(菩提寺がある場合は特に配慮が必要)
- 授与: 僧侶が故人にふさわしい戒名を考え、葬儀(通常は通夜か告別式)の際に授与します。白木位牌に墨書きされます。
- お布施(戒名料)のお渡し: 通常、葬儀のお布施と合わせてお渡しします。「小さなお葬式」の定額プランの場合は料金に含まれています(基本ランクの場合)。
戒名は高額になる場合もあるため、ランクや費用について、家族や僧侶とよく相談することが大切です。費用を抑えたい場合は、最も一般的な「信士・信女」ランクを選ぶなどの選択肢があります。
無宗教や神式の場合、お坊さんなしでも大丈夫?
葬儀の形式は仏式だけではありません。無宗教や神道(神式)など、他の形式で葬儀を行う場合、お坊さんの手配は不要です。
- 特定の宗教儀礼にとらわれない
- 故人らしさを尊重した自由な形式
- (黙祷, 献花, 音楽, 思い出の品など)
- お坊さんなしで司会者が進行
- 「小さなお別れ葬」プランが最適
- 他プランでも寺院手配なしで可
- 神道の教えに基づく葬儀
- (通夜祭, 葬場祭など)
- 神職(神主)が儀式を執り行う
- 対応可能
- プラン追加料金は不要
- 神職への謝礼(御祭祀料)は別途
- 牧師や神父が儀式を執り行う
- 対応可能
- プラン追加料金は不要
- 牧師/神父への謝礼は別途
- 僧侶を呼ばないことが多い
- 学会の儀典長などが導師役
- 対応可能



結論として、無宗教の場合はお坊さんは全く必要ありません。神式やキリスト教式の場合は、それぞれの宗教の聖職者が必要であり、お坊さんは不要です。
押さえておきたい!小さなお葬式を利用するメリット・デメリット


「小さなお葬式」は多くの支持を集める一方で、注意すべき点も指摘されています。利用を検討する上で、メリットとデメリットを客観的に把握しておくことが重要です。
メリット:費用が明瞭、全国対応、実績が豊富で安心など
セットプランで価格が明確。
低価格で予算が立てやすいです。
広範なネットワークで全国どこでも利用可能。
(一部地域除く)
累計52万件以上の実績。
経験と信頼の証です。(業界トップクラス)
顧客満足度96%(自社調査)。
コスパや対応が評価されています。
いつでも繋がるコールセンター。
万が一の時も安心。
パッケージ化で選びやすい。
小規模・シンプル葬に特に適しています。
菩提寺がない場合、
定額のお布施でお坊さんを依頼できます。
資料請求や早割などで
費用をさらに抑えられる可能性があります。






デメリット:一部プラン外費用、提携葬儀社による違いの可能性など
一方で、「小さなお葬式」の利用には以下のようなデメリットや注意点が指摘されています。
依頼前に要チェック!
定額イメージでも、追加費用が発生する場合あり。
総額見積もりで確認を!
施行は提携葬儀社。
担当により質や対応に差が出る可能性。
基本はパッケージ。
希望追加はオプションで費用増に注意。
本体は仲介・手配役。
現場との認識ずれが生じる可能性も。
提携社の利益確保のため、
オプションを強く勧められるケースも?
効率化の一方で、
きめ細やかな対応が不足と感じる場合も。
菩提寺がある場合は必ず事前に相談・許可を。
トラブル回避のため。






「小さなお葬式」は「仲介プラットフォーム」であるというビジネスモデルを理解し、低価格と利便性を享受する一方で、サービスの質の一貫性や個別対応には限界がある可能性を認識しておくことが重要です。
小さなお葬式の利用手順|相談から葬儀後までの流れ


実際に「小さなお葬式」を利用する場合、どのような流れで進むのでしょうか。ここでは、事前相談から葬儀後の手続きまでをステップごとに解説します。
ステップ1:事前相談・資料請求
- 情報収集: 公式サイト閲覧、無料の資料請求。
- 【ポイント】資料請求で割引特典(例:5万円割引)が得られる場合が多いです!
- 電話相談: 24時間対応コールセンターで疑問解消、見積もり依頼。
- 事前準備(推奨): 生前に相談・意向を固めておくことで、いざという時の負担軽減。生前契約プランも有り。






ステップ2:逝去後の連絡・搬送依頼(24時間対応)
- 逝去の連絡: 24時間対応コールセンターに電話。
- 情報提供: 故人名、場所、連絡者情報などを伝える。
- 搬送手配: 「小さなお葬式」が提携葬儀社に連絡し、寝台車を手配。
- ご遺体搬送: 指定場所へお迎え、安置場所(自宅 or 安置施設)へ搬送。
緊急連絡先の電話番号は、事前に控えておくといざという時に慌てません。(公式サイト等でご確認ください)
ステップ3:担当者との打ち合わせ・プラン確定
- 安置後、打ち合わせ: 提携葬儀社の担当者と詳細な打ち合わせ。
- 場所: 自宅、葬儀社事務所など、都合の良い場所で。
- 決定事項:
- プラン最終確認(直葬、自宅葬対応可否、家族葬など)
- 日程・場所決定(火葬場予約など)
- 喪主決定
- 宗教・宗派確認、寺院手配要否
- 祭壇、棺、遺影、オプション選択
- 参列者概数
- 費用詳細見積もりと契約内容確認(最重要!)
- 契約: 全てに納得したら正式契約。
【打ち合わせの注意点】 この打ち合わせで具体的な内容と費用が決まります。疑問点や不安な点は必ず解消し、特に「追加料金が発生する可能性のある項目」を全て確認してください。 担当者とのコミュニケーションも重要です。
ステップ4:葬儀当日の流れ(プランによる)
決定したプランに沿って葬儀を執り行います。当日の流れはプランによって大きく異なります。
- 小さな火葬式: (多くの場合)火葬場で集合 → 炉前でお別れ → (炉前読経) → 火葬 → お骨上げ
- 小さな一日葬: (午前~)式場集合 → 納棺 → 告別式 → お別れ → 出棺 → 火葬・お骨上げ → (精進落とし)
- 小さな家族葬・一般葬: 【1日目】(午後~)式場集合 → 納棺 → 通夜式 → 通夜ぶるまい 【2日目】(午前~)葬儀・告別式 → お別れ → 出棺 → 火葬・お骨上げ → 精進落とし



ステップ5:葬儀後の手続き・アフターサポート
葬儀後も様々な手続きや供養が続きます。「小さなお葬式」では、関連するサポートも提供しています。
- 遺骨の安置: 自宅の後飾り祭壇などに一時安置。
- 諸手続き: 死亡届提出(葬儀社代行)、年金・保険、名義変更、相続など。
- 法要: 四十九日、一周忌などの寺院手配サービスあり。
- 納骨: お墓や納骨堂への納骨。
- アフターサポート例:
- 諸手続きのアドバイス
- 仏壇・本位牌・お墓の相談・紹介
- 香典返し、遺品整理の相談・紹介
- 永代供養、海洋散骨などの納骨先紹介



小さなお葬式のプランに関するよくある質問(FAQ)


「小さなお葬式」の利用を検討する際に、多くの方が疑問に思う点について、Q&A形式でお答えします。
- ご遺体の安置について(付き添い安置・面会は可能?)
. 自宅安置、または安置施設を利用します。付き添いや自由な面会はオプションとなる場合が多いです。
- 安置場所: 自宅 または 提携の安置施設。
- 安置期間: 最低24時間。通常2~3日(プラン規定日数あり、超過は追加費用)。
- 面会:
- 自宅安置:比較的自由。
- 安置施設:可能だが時間制限・予約要の場合が多い。
- 小さなお別れ葬プラン: お預かり安置のみで、対面での面会は基本的に不可。
- 付き添い安置: 故人と宿泊できる施設はオプション(例:1日あたり55,000円)。全ての施設で可能ではない。
希望する場合は、必ず事前に相談し、対応可能なプラン、オプション、追加費用を確認してくだ
- ドライアイスの追加費用は発生する?
A. はい、プランの規定日数(例:3日間)を超過した場合は発生します。
- ご遺体の保全に不可欠ですが、安置日数が延びると追加が必要になります。
- 追加費用目安: 1日あたり 約5,000円~15,000円(地域・季節による)。
- 想定外の追加費用になりやすい項目なので、超過した場合の料金体系を事前に確認しましょう。
- 骨壷の種類や費用はプランに含まれる?
A. 基本的な骨壷・骨箱は主要プランに含まれます。種類を選ぶ場合は追加費用が必要です。
- 含まれるもの: 白無地陶器製などの基本的な骨壷と桐箱など(「小さなお別れ葬」にも含む)。
- 選択・オプション: 色柄付き、大理石製、手元供養用のミニ骨壷などを希望する場合はオプションとなり、追加費用が発生します(市場価格例:一般骨壷1~5万円)。
- 「小さなお葬式」でどの程度選択肢があるか、費用はいくらかは直接確認が必要です。
- 霊柩車の種類やグレードは?
A. 標準はバン型寝台兼用霊柩車の可能性が高いです。宮型などはオプションです。
- 役割: 主に式場から火葬場への棺搬送用。
- 標準プラン: 費用を抑えるため、シンプルなバン型・ワゴン型が多いと考えられます。(口コミでは選択できた例も)
- オプション: 伝統的な「宮型」や高級車ベースの「洋型」を希望する場合は追加費用で手配可能か確認が必要(目安:33,000円~)。地域によっては手配困難な場合も。
- 参列者の人数に制限はある?
プラン料金自体に厳密な制限はありませんが、会場規模による実質的な制限があります。
- プラン別目安: 直葬(~10名)、一日葬(5名~)、家族葬(10名~30名程度)、一般葬(30名~)。
- 実質制限: 各プランで想定された会場の収容人数を超える場合、参列者に不便が生じる可能性あり。
- 費用への影響: 人数が増えてもプラン料金は変わらないが、飲食費・返礼品費(プラン外)は人数に応じて増加します。
- 大人数を想定する場合は、対応可能なプランや会場があるか事前に相談が必要です。
- 「のりかえ割」について教えて!
A. 他社の互助会等の積立金を「小さなお葬式」の費用に充当できる割引制度です(条件あり)。
- 他の葬儀社の積立・互助会に加入している方が対象。
- 割引額:最大150,000円(※条件により変動)。
- 適用条件、手続き、対象となる積立サービスの詳細などは、「小さなお葬式」に直接問い合わせて確認が必要です。






まとめ:後悔しないお葬式のために|あなたに合った小さなお葬式のプランを選びましょう


「小さなお葬式」は、費用を抑えたい、シンプルな葬儀をしたい、全国どこでも対応してほしい、といった現代のニーズに応える葬儀サービスとして、累計52万件以上の実績を積み重ね、多くの方に選ばれています。
その低価格は、サービスの絞り込み、提携ネットワークの活用、小規模葬儀への特化によって実現されています。
24時間365日のサポート体制も、いざという時の大きな支えとなるでしょう。
特に、儀式を省略し火葬のみを行う「小さな火葬式」プランは、費用を最小限に抑えたい場合に適しています。
ただし、このプランには儀式用の祭壇は含まれず、火葬料金や規定を超える安置・ドライアイス費用などが別途必要になる点には注意が必要です。
自宅での葬儀(自宅葬)については、「小さなお葬式」に専用プランは明記されていませんが、提携葬儀社を通じて対応可能な場合もあります。
自宅葬は、住み慣れた家でのお別れというメリットがある一方、スペースの確保や近隣への配慮、遺族の負担増といった課題もあります。
希望する場合は、対応可否や費用、準備について、「小さなお葬式」に直接、詳細を確認することが不可欠です。
祭壇は、火葬式プランには含まれませんが、一日葬以上のプランには標準で生花祭壇が含まれます。
より華やかにしたい場合は、費用はかさみますがオプションでグレードアップも可能です(+数万円~70万円以上)。葬儀後の自宅での供養に必要な後飾り祭壇は、多くのプランに含まれています。
お坊さんの手配も、定額のオプションサービス(8万円~20万円程度、戒名料込み)として提供されており、お寺とのお付き合いがない場合でも仏式の葬儀を行えます。
ただし、菩提寺がある場合は、必ず事前に相談することがトラブル回避のために最重要です。無宗教や神式など、仏式以外の形式にも対応可能です。
「小さなお葬式」を利用するメリットは、費用の明瞭さ、全国対応、豊富な実績、割引制度など多岐にわたります。
しかし、追加料金が発生する可能性や、提携葬儀社によるサービスのばらつき、仲介業者としての限界といったデメリットも存在します。
【後悔しないための最終確認】
- 総額費用を必ず確認! (基本プラン + 火葬料 + オプション + 追加料金)
- プラン内容を徹底理解! (含まれるもの、含まれないもの)
- 菩提寺がある場合は最優先で相談!
- 家族・親族とよく話し合う!
- 疑問点は全て質問・解消する!
後悔しないお葬式のためには、まず故人の遺志と遺族の希望を尊重し、どのようなお別れをしたいかを考えることが第一歩です。
その上で、「小さなお葬式」の各プランの内容、メリット・デメリット、追加料金が発生する可能性のあるケースを十分に理解し、必要であれば事前に資料請求(割引特典あり!)や無料電話相談を活用して疑問点を解消しましょう。
そして、ご自身の状況や予算に最も合ったプランを慎重に選ぶことが大切です。